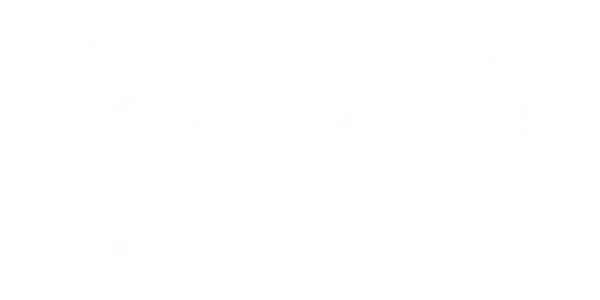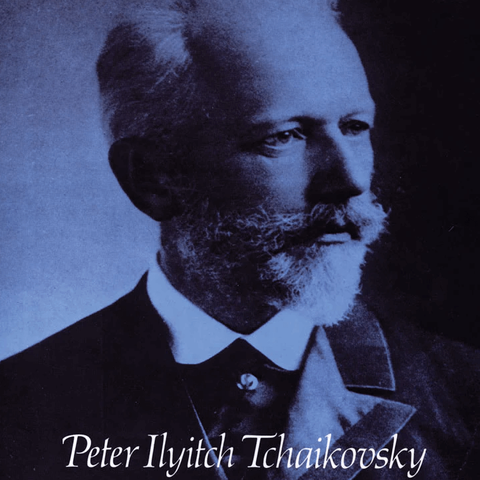「 「人生」というテーマを曲に書きたい チャイコフスキーのミステリアスを演出する交響曲《悲愴》」を通販レコードとしてご案内します。
11月6日
ロシアの作曲家、チャイコフスキー没(1840〜1893)
チャイコフスキーは1891年に変ホ長調の交響曲(自身で『人生』と言うタイトルをつけていた)を途中まで書きすすめていましたが、突然にピアノ協奏曲第3番に描き直します。しかしこの「人生」というテーマを曲に書きたいという思いは彼の中で引き継がれていたようで、それが形となったのが《悲愴交響曲》。
作曲は1893年2月17日に第3楽章から着手。この高揚感満点の楽章は最初から第3楽章だったのでしょうか?
ともかくも半年後の8月25日にはオーケレストレーションまで一気に完成し、同年の10月16日(グレゴリオ暦では10月28日)に作曲者自身の指揮によりペテルブルクで初演された。あまりに独創的な終楽章もあってか初演では当惑する聴衆もいたものの、いつもならば聴衆の反応、批評に寄って書き直したりもするチャイコフスキーも、この曲に対しては自信が揺らぐことはなかったようです。
しかし大成功の初演のわずか9日後にチャイコフスキーはコレラに感染、肺水腫が原因で急死。この曲は彼のミステリアスを演出するのには他にない音楽になっています。
チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調、作品74「悲愴」
TCHAIKOVSKY: SYMPHONY No.6 IN B MINOR, Op. 74 “PATHÉTIQUE”
チャイコフスキーの「悲愴」交響曲。
チャイコフスキーが、彼の第6交響曲のスケッチをはじめたのは1893年のはじめ頃、やがて53歳になろうとしていたときである。
この年の初夏にイギリスにゆき、ロンドンのフィルハーモニック協会の演奏会で自作の指揮をしたり、ケンブリッジ大学より音楽博士の学位をおくられる式に出席して帰国したのが6月であった。帰国後その完成に全力をあげて、9月には完成していた。チャイコフスキーは1888年に第5交響曲を発表したあと、1892年から新しい交響曲の構想をたてスケッチをはじめていたのだが、93年早々に、このスケッチを破棄して、まったく別なプランから出発したのが現在の第6交響曲であった。チャイコフスキーはこの新作についてはなみなみならぬ自信をもっていたようで、弟のモデストにも、「わが生涯の最大傑作だ」といっていたくらいであった。そして、単に第6交響曲というだけでは何としても物たりなくおもい、曲にふさわしい標題になる言葉をあれこれとさがしていたがなかなか適当なものが得られず、一時は、単に「標題交警曲(Program Symphony)」と呼ぼうと考えていたようである。そうし たときのある日、兄からこの件について相談をうけていた弟のモデストが、「悲劇的(Tragic)」 というのはどうだろうといったのにあまり動かされる様子もなかったチャイコフスキーではあったが、つづいて、では「悲愴(Pathétique)」というのは、ともちだされて、即座に「それだ!」と叫んで、一瞬にしてきまってしまったという。
この年の初夏にイギリスにゆき、ロンドンのフィルハーモニック協会の演奏会で自作の指揮をしたり、ケンブリッジ大学より音楽博士の学位をおくられる式に出席して帰国したのが6月であった。帰国後その完成に全力をあげて、9月には完成していた。チャイコフスキーは1888年に第5交響曲を発表したあと、1892年から新しい交響曲の構想をたてスケッチをはじめていたのだが、93年早々に、このスケッチを破棄して、まったく別なプランから出発したのが現在の第6交響曲であった。チャイコフスキーはこの新作についてはなみなみならぬ自信をもっていたようで、弟のモデストにも、「わが生涯の最大傑作だ」といっていたくらいであった。そして、単に第6交響曲というだけでは何としても物たりなくおもい、曲にふさわしい標題になる言葉をあれこれとさがしていたがなかなか適当なものが得られず、一時は、単に「標題交警曲(Program Symphony)」と呼ぼうと考えていたようである。そうし たときのある日、兄からこの件について相談をうけていた弟のモデストが、「悲劇的(Tragic)」 というのはどうだろうといったのにあまり動かされる様子もなかったチャイコフスキーではあったが、つづいて、では「悲愴(Pathétique)」というのは、ともちだされて、即座に「それだ!」と叫んで、一瞬にしてきまってしまったという。
チャイコフスキーが「悲愴」と命名した第6交響曲は1893年10月28日に、彼自身の指揮で時のロシアの首都ベテルスブルク (現在のレニングラード)で初演された。その初演から4日後、チャイコフスキーはレストランでのんだ生水から、当時蔓延していたコレラに感染し、わずか5日間床についたきりで11月6日にこの世を去ってしまったのである。11月18日に行なわれたチャイコフスキーの追悼演奏会で、再び「悲愴」交響曲が演奏されたとき、会場は作曲家の急逝を惜しむ聴衆の嗚咽の声に満たされたという。いずれにせよ、チャイコフスキーが、最後の作品に「悲愴」という標題を附し、あわただしくこの世を去ってしまったのは偶然というにはあまりにも運命的なものでもあったというほかはない。
チャイコフスキーがこの作品をとくに「悲愴」と命名した、感情表現の深刻さは、たとえば、その極端なダイナミックス記号の指定にも見られる。ピアニッシモは3個の〝p〟、フォルティッシモは3個の〝ƒ〟で指定されるのが普通であるが、彼は、〝p〟を6個、〝ƒ〟を5個もつけているところがある。
これは物理的な音量の指定ではなく、心理的な指定だと解さるべきであろうが、そうした点にも、チャイコフスキーがこの曲に深刻なエモーションの起伏を要求した姿勢がはっきりとうかがい知れるだろうとおもう。
編成は、フルート3 (うち、ピッコロに持替1)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット3、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、バス・チューバ1、ティンパニ3、タムタム(終楽章のみ) 1、弦。
これは物理的な音量の指定ではなく、心理的な指定だと解さるべきであろうが、そうした点にも、チャイコフスキーがこの曲に深刻なエモーションの起伏を要求した姿勢がはっきりとうかがい知れるだろうとおもう。
編成は、フルート3 (うち、ピッコロに持替1)、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット3、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、バス・チューバ1、ティンパニ3、タムタム(終楽章のみ) 1、弦。
第1楽章 ― アダージョアレグロ・ノン・トロッポ
曲はコントラバスに支えられ、ファゴットの最低音域で奏されるうめくような、アダージョの序奏主題(ホ短調、4/4拍子)からはじまる。沈痛で陰鬱なこの開始部は、終楽章と呼応して、この作品の「悲愴」という性格をはっきりと規制したものといえよう。
19小節目で、アレグロ・ノン・トロッポ(ロ短調)の主動にはいる。ヴィオラとチェロによるくらい音色のなかに不安と焦燥感のこもったような第1主題は、70小節に及ぶながい間こやみなくうごきつづけ、最後に速度をおとしてハタときえる。ついで、アンダンテ(ニ長調)で弱音器つきの弦に第2主題が詠歎的にうたいあげられる。そのあと、第1主題と第2主題が交互に現われ、クラリネットからファゴットにうつる最弱音で160小節に及ぶ長大な呈示部がおわるが、ここに〝p〟が6個つけられている。
展開部は急激な感情の爆発をおもわせる叩きつけるような最強音の第1主題からはじまり、トランペットとトロンボーンによる新しい素材の発展をおりこみ、第2主題による息づまるようなフガートのクライマックスを築きあげてゆく。この緊張感は再現部にももちこされ、ふたつの主題が深刻に処理される。終結部はアンダンテで、展開部の金管の素材(これはロシアの葬送の音楽からとられたものだといわれている)に呼応する弦のピッチカートの下降音型の反覆に、ティンパニが重苦しいリズムを刻み、やがて消え去ってゆく。
19小節目で、アレグロ・ノン・トロッポ(ロ短調)の主動にはいる。ヴィオラとチェロによるくらい音色のなかに不安と焦燥感のこもったような第1主題は、70小節に及ぶながい間こやみなくうごきつづけ、最後に速度をおとしてハタときえる。ついで、アンダンテ(ニ長調)で弱音器つきの弦に第2主題が詠歎的にうたいあげられる。そのあと、第1主題と第2主題が交互に現われ、クラリネットからファゴットにうつる最弱音で160小節に及ぶ長大な呈示部がおわるが、ここに〝p〟が6個つけられている。
展開部は急激な感情の爆発をおもわせる叩きつけるような最強音の第1主題からはじまり、トランペットとトロンボーンによる新しい素材の発展をおりこみ、第2主題による息づまるようなフガートのクライマックスを築きあげてゆく。この緊張感は再現部にももちこされ、ふたつの主題が深刻に処理される。終結部はアンダンテで、展開部の金管の素材(これはロシアの葬送の音楽からとられたものだといわれている)に呼応する弦のピッチカートの下降音型の反覆に、ティンパニが重苦しいリズムを刻み、やがて消え去ってゆく。
第2楽章 ― アレグロ・コン・グラツィア
悲劇的な第1楽章から一転して、憩いのひとときを感じさせるこの楽章は、古典交響曲のメヌエットにあたるような明るさをもっており、優麗なチャイコフスキー好みの旋律が感傷的にうたいあげられる。5/4拍子という変則のリズムはロシア民謡によく見られるものだが、2拍子+3拍子の結合で、耳に響くリズム感はむしろ、チャイコフスキーが得意としたワルツに似ている。このやすらぎにあふれたニ長調の舞曲も、中間部ではロ短調に転じ、ティンパニとコントラバスの執拗な2音の連続が、悲劇的なくらい影を投じている。
第3楽章 ― アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ
いわゆるスケルツォ楽章にあたるわけだが、主題は行進曲風のリズムがきわだっている。まず、弦による12/8拍子のリズムをバックに、オーボエが4/4拍子でスケルツォ主題を出す。この主題が行進曲風の足どりになったり、スケルツォ風なうごきを示したり、変化しながら、はじめは断片的だった主題のかたちが、次第に全貌を現わしてゆく。チャイコフスキーの構成とオーケストレーションのうまさを遺憾なく示した部分といえよう。
第4楽章 ― アダージョ・ラメントーソ
この終曲は、この作品が書かれた当時としては、型破りの交響曲の終楽章であったといえる。絶望感をあおるような暗渡たる気分の第1主題がヴァイオリンに現われる。この主題は第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンが交互に1音符ずつ弾いているので、旋律がとぎれとぎれとなってすすりなくような効果をうみ出しているのがとくに注目される。第2主題はアンダンテで、ホルンによって導入される、シンコペーション・リズムに支えられて、弦が最弱音で歌いあげる悲痛なものである。そのあと、第1主題が、アンダンテ・ノン・タントで再現されるが、弦のユニゾンによって、呈示部よりもさらに沈潜した悲劇性が昂揚され、トロンボーンとタムタムがそのトラジックな響きを一層強調する。ついで現われる第2主題も、呈示部のニ長調から、口短調に転調されてくらさを加えてゆく。そして、曲はくらい沈黙の世界へとおもくるしい足どりをすすめてゆくのである。
ハネカーは人間の魂をゆする葬送の音楽として、ベートーヴェンの第3交響曲の「葬送行進曲」やワーグナーの「ジークフリートの葬送の音楽」以来の傑作であると、この終楽章のオリジナリティと表現の見事さを高く賞賛している。
ハネカーは人間の魂をゆする葬送の音楽として、ベートーヴェンの第3交響曲の「葬送行進曲」やワーグナーの「ジークフリートの葬送の音楽」以来の傑作であると、この終楽章のオリジナリティと表現の見事さを高く賞賛している。
from 100年後でも聴いて楽しいアナログ名盤レコード https://ift.tt/pF0eSow
via IFTTT