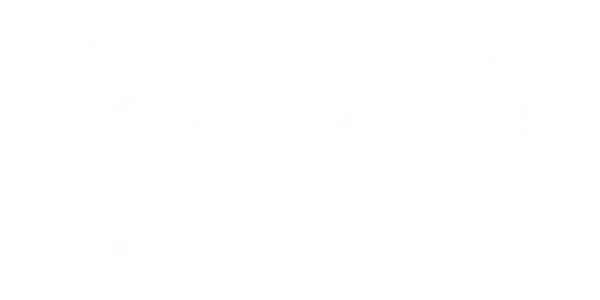「 GB DECCA SXL6169 ヘルベルト・フォン・カラヤン ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ドヴォルザーク 交響曲8番」を通販レコードとしてご案内します。
DECCAでの短いが幸福な時期。オーケストラを信頼しきった芸術家本来の姿が感じられる。 ― 優美な歌と音色の魅惑に満ちた、ヘルベルト・フォン・カラヤンのウィーン時代の最高の成果の一つ。戦前は弦の黄金美の放射が凄まじかったウィーン・フィルハーモニー管弦楽団。この〝ウィーンの香り〟と喩えられる、絹のような弦楽器、チャルメラのようなオーボエ、まろやかなフルートの音色、柔らかでフワッとしながらも力強いウィンナ・ホルンの音が何とも優雅な、独特の音色を保っていた楽団をカラヤンの指揮で聴くことが出来たのは幸福なことだ。レコード録音に対して終生変わらない情熱を持って取り組んだカラヤンが、一時代を画した事になったのが英デッカでのウィーン・フィルとのステレオ録音プロジェクト。1959年、カラヤンはウィーン・フィルとのインド、日本、アメリカへの40日間の演奏旅行を控え、とくにアメリカでの自らのLPレコードの販路強化のために、米RCAと提携したばかりの英デッカと契約を結びます。カラヤン&ウィーン・フィルが演奏旅行の曲目としていたベートーヴェンの交響曲第7番、ブラームスの交響曲第1番などが事前にセッション録音され、日本やアメリカを訪れたタイミングでそのLPレコードが発売される、といういかにもカラヤンらしいスケジュールが組まれ、実行されました。演奏内容も50歳代前半の颯爽としたカラヤンの指揮に黄金時代のウィーン・フィルが最高のアンサンブルで応え、それを英デッカの優秀録音で存分にとらえきった名曲・名盤・名演奏揃いとなっています。当曲が録音された1961年は、5月にマリオ・デル=モナコ、レナータ・テバルディとのヴェルディの歌劇「オテロ」全曲盤、6月にレオンティン・プライスとのクリスマス・アルバムという名盤を相次いで録音し、9月にウィーン国立歌劇場のシーズンが始まると、オペラ上演と平行してウィーン・フィルとは、当アルバムのみならず、チャイコフスキー「くるみ割り人形」、グリーグ「ペール・ギュント」、アダン「ジゼル」、ホルスト「惑星」など、LPレコードにして実に5枚分に相当する録音を集中的に行なっています。同じ時期の定期演奏会では録音曲目であるドヴォルザークの交響曲第8番《イギリス》を取り上げています。LP初発はSXL-6169 (1965年4月、日本盤初発は翌66年4月)。この1961年9月~10月のセッションのあと、米RCAのために録音されたプッチーニの歌劇「トスカ」とビゼーの歌劇「カルメン」の全曲盤を除くと、ウィーン・フィルとは1965年までにLP2枚分を録音したにすぎず、1961年暮れから始まるベートーヴェンの交響曲全集、1963年に始まるブラームスの交響曲全集など、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とのドイツ・グラモフォンへの録音により大きな比重が置かれるようになっていきました。名プロデューサー、ジョン・カルショーとのコラボレーションによってウィーン・フィルと進められた英デッカへの録音は、ちょうどステレオ録音が導入されて活気付いていたレコード市場を席巻する形になりました。その中でも特に充実した演奏と評価の高い1961年録音のドヴォルザークの交響曲第8番《イギリス》です。指揮者のニコラウス・アーノンクールがインタビューに答えて言っていたことによると、若い時のドヴォルザークは次々とメロディが湧き過ぎて困り、かえって良い曲が書けなかったのではないかと思うそうです。それを抑えて制御する術を身に付けてはじめて大作曲家になったのだと。天上からインスピレーションが降ってきても、それを見事に活かせるのは才能と技術の習熟のタイミングが大事でしょう。ブラームスが嫉妬しつつも尊敬していたというドヴォルザークのメロディを生み出す才能、それは「新世界」交響曲にも、弦楽四重奏曲「アメリカ」にも見られますが、一曲の中に次々と惜しげなく印象的なメロディーが出て来てもったいないぐらいの曲が、交響曲第8番《イギリス》です。その制御する術をドヴォルザークが身に付けるのが、交響曲第7番からだと、わたしは考える。カラヤンの天才は、機をとらえる巧さにある。英EMIのウォルター・レッグが、戦後にロンドンで新設されたフィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者の地位を提供したとき、カラヤンは一瞬もためらわずに引き受けた。彼のことをまったく知らない国に活動の場が与えられるだけではない。レッグが選りすぐった ― おそらくはロンドン史上最高のオーケストラの実権が与えられ、さらにオーケストラ曲とオペラを望むだけ録音できる、ほとんど無限の機会が与えられたのだ。ウィーン・フィルと専属関係を結んだ英デッカは、この結束を強めるためには、デッカが何か大きな仕掛けをすることが必要だった。中でもいちばん効果的なのは、ウィーン・フィルも含めた全員が不可能だと考えていたこと、すなわちカラヤンを獲得することだった。カラヤンは、アドルフ・ヒトラーの死によって生じた、指導者を渇望するドイツ人の魂の空白を、無意識のうちに埋めていた。彼のしぐさは型にはまっていた。気まぐれで無慈悲で、無遠慮だった。並はずれて聡明で、見栄えをよくすることに神経を注いでいた。言葉を変えれば、洗練された、あるいはわざとらしいオーラを放っていて、胸がむかつくほどだった。見栄えをよくすることに心血を注いだカラヤンの演奏が、「悪かろう」はずがない。その上、カルーショーの理解も手伝って、その録音群は、いかにもカラヤンらしい「完璧な」録音であると同時に、音楽を知るという意味ではもちろんのこと、音楽を堪能するという意味においても50年を経た今もまったく色褪せない。
- Record Karte
- 1961年9月&10月、プロデュースと録音はショルティの《ニーベルングの指環》製作者のジョン・カルーショー、ゴードン・パリー、そしてセッションは音響抜群のゾフィエンザール。
from 100年後でも聴いて楽しいアナログ名盤レコード https://ift.tt/ITsqJaY
via IFTTT